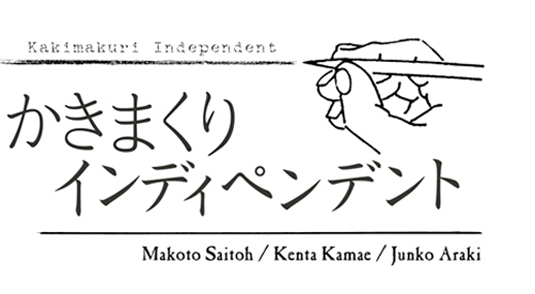会田誠初主演、松蔭浩之第一回監督作品『砂山』
@ミヅマアートギャラリー
短編においてあらすじは知らずに観た方がいい。私は松蔭さんの原作も読まずに、上映会場に向かった。
その夜、飯田橋駅からミヅマアートギャラリーまでの道沿いは、早咲きの桜が満開だった。3月30日(土)、ミヅマアートギャラリーでは、松蔭浩之第一回監督作品『砂山』の完成記念上映イベントが開催された。原作は松蔭さんが17年前に執筆したもので、会田誠さん初主演の短編映画作品であった。活弁映画監督の山田広野さんによる『瓶詰め男』、撮影を担当した監督の金子雅和さんによる新作『逢瀬』の上映に続き、いよいよ『砂山』が上映された。
最初の場面で、「もしかしたらパロディ色の強い作品なのだろうか?」と思ったが、そんなのはすぐに打ち消された。『逢瀬』のあまりにも美しいエンディングのせいか、立て続けに観た『瓶詰め男』シリーズのひとコマがデジャヴュのように蘇ってきたから?一連の上映の流れが、松蔭さんの演出だったのかもしれないとさえ思えた。だとすると、それは見事に完璧な演出だった。
18分の作品は、見終えた直後にスタンディングオベーションしたいほどに感動的なものだった。フランス映画好きならばたまらないはずのシーンでうめ尽くされていたからだ。
18分の作品は、見終えた直後にスタンディングオベーションしたいほどに感動的なものだった。フランス映画好きならばたまらないはずのシーンでうめ尽くされていたからだ。
何よりも色彩が美しく、光の具合は絶妙で、会田さんをあれ程美しく撮れるのは松蔭さんを置いてほかにいないだろうと強く感じた。
会田さんは男の色香をスクリーンだけではなく会場全体に漂わせていた。
フランス映画のベッドシーンに特有の音楽を伴わない効果。それはとてもリアルで、だからとてもエロティックで、女性目線で言わせていただくと、愛撫シーンは最高にセクシーだった。シャツの隙間だけ日焼けした肌も(あれはメイク?それともリアルなもの?そんなことはどうでもいいが)、体臭を伴うような息を止めてしまうほどのリアル感を漂わせていた。
薄い黄色のリネンシャツのよれ具合も、ボタンの外し具合も、パンツの丈の長さも、裾の折り具合も、ヘアースタイルも髭の長さも、すべてに隙がなく、でも自然で。
映画の途中、途中に挿入されているクラシック音楽は、シーンとシーンを絶妙に繋げていた。
アトリエで赤い作品を描いているシーンでは、女が足の指を男の顔近くにのばして、青いペディキュアが塗られた足のまん中の指に赤い絵の具を塗るシーンがとても好き。実際には観たことがないのに、日活ロマンポルノみたいな淫靡な感じが漂っているように感じられたから。赤い画面の中に見え隠れする足指の青のペディキュアの色は、ゴダール作品の赤と青を彷彿とさせるものでもあった。
砂山を積み上げるシーン。男がもがき苦しんだ途端に画面が切り替わったから、スキンヘッドの青年は、あちらの世界とこちらの世界の境界線にいる道先案内人なのかと思えた。作った砂山を崩せと言った途端青年は消えて、瞬間、男がこちらの世界に戻ったのかなと。
砂山を積み上げるシーン。男がもがき苦しんだ途端に画面が切り替わったから、スキンヘッドの青年は、あちらの世界とこちらの世界の境界線にいる道先案内人なのかと思えた。作った砂山を崩せと言った途端青年は消えて、瞬間、男がこちらの世界に戻ったのかなと。
砂山を崩すシーンを見ながら、映画『砂の女』のワンシーンを思い浮かべていた。
『砂の女』では、砂の穴の中から必死に這い上がろうともがく男がいて、穴の中に引き留めたい女がいた。
砂山を作りきったところで女に壊させるシーンに、『砂の女』に登場する男と女とは絶対的に異なった対極にあるシーンだと感じた。それは、とても現代的であり、なにかポジティブな空気に包まれているように見えた。
砂山を作りきったところで女に壊させるシーンに、『砂の女』に登場する男と女とは絶対的に異なった対極にあるシーンだと感じた。それは、とても現代的であり、なにかポジティブな空気に包まれているように見えた。
最初のシーツの山と最後の砂の山。
最初の山は、本能的な性的欲望。一日の始まりは≪拒まれる≫シーンで始まった。
赤い絵、赤いペディキュア、赤い激痛、そして残像。
最後の砂の山は、性欲を含んださまざまな欲望。それらは、金欲や出世欲や独占欲。
それまで必死になって造り上げてきた山だったけれど、男は女に≪「おまえに壊して欲しい」≫と言い、女が砂の山を蹴飛ばして崩していく。
それまで必死になって造り上げてきた山だったけれど、男は女に≪「おまえに壊して欲しい」≫と言い、女が砂の山を蹴飛ばして崩していく。
二人の関係が少し変わった、男の想いが変わった一日。
ラストシーンの絵画のような美しい風景の中を、男と女が右から左へと消えていく。
今もその映像が蘇ってくる。
上映後に行なわれた、会田さん、松蔭さん、そしてゲストの辛酸なめ子さんによるトークで、原作では女が死んでしまうと言っていたが、映画ではそうじゃなくて良かったと感じた。女が死んでしまうと、それは『髪結いの亭主』みたいに切なすぎるから。
映画の中で、男の頭の中の想いを語るシーンにフランス語が用いられていた。
観客の女性が「なぜフランス語?(だっただろうか・・・)」と尋ね、松蔭さんは解らないといった顔をして≪とぼけているな≫と思った。(そう思ったのは、私だけだったのだろうか・・・)フランス語的な思考であろうとなかろうと、そんなことはどうでもいいのだ。
≪フランス語である必要があった≫はずだし、≪フランス語である明確な理由があった≫からの確信犯的投入だったに違いないから。そうですよね、松蔭さん?
観客の女性が「なぜフランス語?(だっただろうか・・・)」と尋ね、松蔭さんは解らないといった顔をして≪とぼけているな≫と思った。(そう思ったのは、私だけだったのだろうか・・・)フランス語的な思考であろうとなかろうと、そんなことはどうでもいいのだ。
≪フランス語である必要があった≫はずだし、≪フランス語である明確な理由があった≫からの確信犯的投入だったに違いないから。そうですよね、松蔭さん?
最近観た映画作品の中で一番と言える作品、それが『砂山』。
見終えた直後、「時代はまさに松蔭さんや会田さんの時代になった!」そんなことを感じ嬉しくなった。いくえにも重なった時代のさまざまなエッセンスを全身で吸収してきた世代の時代が始まったのだと。
[文:新城 順子]