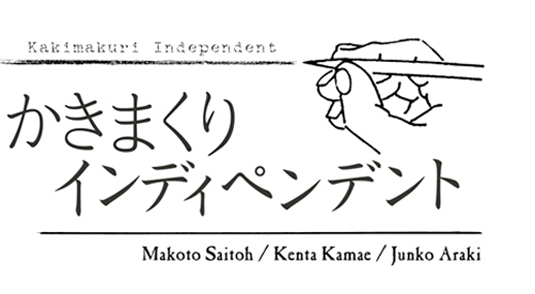古久保憲満・松本寛庸展
UNDER GALLERY 35
『スーパーワールド・オン・ペーパー』
BankART Studio NYK
「アール・ブリュット」の領域を越えて、
繰り広げられる「世界」と終着無き「執着」
先月半ばまでBankARTで開催されていた「UNDER GALLERY 35」。注目をあびる35歳以下のアーティストとプロデュースする立場のギャラリー(マネージャー)がタッグを組むというかたちで、コンクリート剥き出しの無機質な広いスタジオ2.3Fスペースをまたがって6組6様の個性を放つ、有機的な個展空間が展開された。
いま、アーティストすなわち作家側にとって、キュレーターやプロデューサーといった存在との揺るぎない信頼関係は、作風や創作活動に影響を及ぼすほど、切り離すことのできない大きな役割を果たしているのかも知れない。絵画、彫刻、インスタレーションと各チームの表現はさまざまだが、ここでいう「マネージャー」の熱が幾分伝わってきて、作品に何か見えない奥深ささえ与えている気がするのも確かだ。
ただ、そういった趣旨の今回の企画において、一切そのことを超越して目に焼き付いたのが、古久保憲満と松本寛庸、両作家の圧倒的な絵画であった。「スーパーワールド・オン・ペーパー」というタイトル通り、まさに紙の上に、彼らの驚愕の世界観が広がっているのだ。
一般的には「アール・ブリュット」や「アウトサイダー・アート」というと、知的障害者や自閉症などの精神障害者によるアートと単純に解釈されがちだが、本来はアートの教育を受けずに、またその恩恵による発表の場やコネクションを持たずして、独学での表現、独自の活動に根差すことで創作意欲を築き上げてきた作家のつくるアート作品を指す。
二人の作家にどのようなハンディがあるかなどといった問題はそもそも関係が無い。とにかくその緻密さと大胆さが同居したドローイングと無限の色彩感覚は、群を抜いて素晴らしいからだ。二人の絵画に共通するような、建物や飛行機、ドット模様やフラッグといった細かなモチーフのひとつひとつは、少し歪んだフォルムであったり、記号化された二次元的イメージに過ぎないのだが、作品全体を見たとき、構図の軸がしっかりしているといえばいいのか、とてもどっしりとした絶妙なバランス感覚が感じられるのだ。
どちらかといえば、古久保の絵は「線」に、松本の絵は「点」と「面」に、その上手さの妙を感じる。作品の要素となるその妙が「執着」という二人の共通言語でもあるかの如く、気が遠くなる程いくつも重なり、さらにランダムに並ぶのである。以前「アートを綴る」講座で、草間彌生の制作風景の映像を見たことがあったが、草間が大きな紙面に、執拗に彼女の代名詞でもある「ドット」を下書きもなしに、とりつかれたように隅から描き込んでいく。まるで全体の構図などは一見お構いなしである。そんな姿が思い出されシンクロする。古久保と松本もまた、同じような感覚で描き込み、色を重ねていくのであろうか?ただ、完成された絶妙な構図、計算されたような色彩構成に、そのコンセンサスを吹き飛ばすような清々しさが内包されている点において、草間同様、天性のセンスを持ちあわせているとしか表現のしようが無い。
前述した「アール・ブリュット」や「アウトサイダー・アート」という言葉は、単なるカテゴライズのための領域に過ぎない。作品を発表するアーティストにとって、無論、そんな分類に何の意味があろう。自由に解放されたフィールドに障害者も健常者も関係なく、観賞者の魂を揺さぶる独創性や芸術性が有るのか無いのか、そこにアートの大きな価値や意味が存在する。
これから、古久保と松本の描くことへの「執着」は、いったいどこから生まれ、そしてどの世界へ終着するのか? いや、辿り着くという概念は無く、新たな世界へと自在な発想でつき進んで行くに違いない。「アウトサイダー」?! とんでもない。それはきっとこの上なくまっすぐな道だ。いま、目の前に繰り広げられている、外連味の無い彼らの作品こそが、実は生粋のアートなのではないのだろうか。そんな風に思えた。