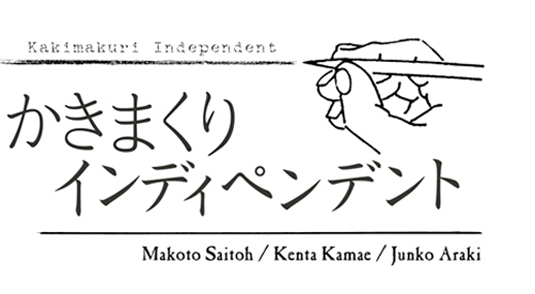08
里山の限界芸術vol.3 上野雄次
『限界花道家☆花いけ大作戦!』
越後妻有 大地の芸術祭の里
気と花と体、そして偶然性。
全てがひとつになった、壮絶「花いけ」パフォーマンス。
上野雄次は、勅使河原宏の前衛的な生け花に出会い華道を学ぶも、そのフィールドを超越した創作活動により、独自の「花いけ」という世界観で表現を展開するアーティストだ。「花いけ大作戦!」と題された今回の企画展は、上野の「花いけ」をさらに凌駕する機会に違いない。里山という恵まれた自然舞台とこの土地に根づく習慣や人々に長期的に関わることで、どのような「花いけ」パフォーマンスを見せるのか興味深かった。
初めて上野のパフォーマンスを目の当たりにするわけだが、常に型破りな大胆さが存在するであろうことは、乗用車に巨大な鳥の巣のような枝木を乗せて(いけて)走る「暴走花いけ限界号」※1 を見れば容易に想像はつく。ただ、今回はここ越後妻有での締め括りとなるハレの場であるということは間違いないだけに、期待も高まる。
パフォーマンスは、「脱皮する家」※2 という古民家で行なわれた。吹き抜けの居間に20人ほどのギャラリーが囲むように座るその輪の中央が、もちろん上野の独壇場の舞台となるであろう。正座して一礼をする上野は、パフォーマンスが始まる合図かの如くパーカーのフードを被る。これは上野が臨戦態勢であることを意味する。中央にどっさりと積まれた里山の草木を前にして、おもむろにとり出した黄色い糸を足の先端から自身の身体全体へと巻き付けていく。一体何が始まるのか予測出来なかったが、巻き終えた糸に目の前の草をひと握り差した瞬間に意表をつかれた。自らの身体に草花を「いける」というのだ。ギャラリーが息を呑んで黙視する中、バサバサと草を自らの身体にいけていく。程なくして上野の身体は草木で全く覆われた。
ワラの衣装に包まれた「なまはげ」のような姿になると、今度は先ほどの黄色い巻き糸を口にくわえ、蜘蛛のようにその糸を垂らしながら家の四方八方いたるところを動き回るのである。柱があろうが、梁があろうが、ギャラリーが居ようがお構いなしだ。取り憑かれたように、ときには吹き抜けの梁によじ登り、縦横無尽に黄色い糸を張り巡らせていく。静かなこの古民家に響きわたるのは上野の息遣いと汗のしたたるような足音だけであったが、途中に突然の雷鳴とともに物凄い夕立が降り出した。それは偶然なのか、上野が呼び寄せた必然なのかわからないまま、雷の閃光と屋根や庇を叩き付ける豪雨の音はパフォーマンスの佳境をさらに演出した。
かれこれ1時間はとうに経過したはずだ。様々な角度に交差する黄色い糸は、まさに蜘蛛の巣の様に放射状に張り巡らされている。木の椅子をその蜘蛛の巣に絡ませた。それは巣に填まった昆虫のようにぶら下がっている。黄色い草花の束を巣に叩き付けたかと思うと、黄色い花びらが乱舞するその花を中央にいける。いよいよ仕上げの「花いけ」である。その花の束は糸の弾力で天地が逆になり下を向いた。予定調和を最後まで裏切る偶然の演出だ。そして、この儀式を封印するかの様に最後の一輪を立て(いけ)る。言うまでも無く上野の「気」はダイレクトにこちら側に伝わって来た。それゆえに、上野は何故ここまで身体を張り、草花と対峙(格闘)しながら表現するのだろう?そんな想いにまで及ぶのである。
武道(とりわけて剣道)に「気剣体一致【き けん たい いっち】」という言葉がある。気合と剣の動き、そして体捌きがつねに三位一体とならなければいけないということだが、上野に置き換えるとそれは「気花体一致」と言えるかも知れない。その三つのバランスがパフォーマンスの出来や間を左右するのではないか。華道のみならず、茶道や武道といった、日本の芸術文化では、「気」や「間」といった要素が古くからの重要な美学の根源と理解されている。上野の場合、花をいけてシンボル化された表現のカタチよりも、その行為の波動に創造力を強く感じるのだ。
今回、彼と同行して印象に残った言葉があった。『花をいけるという行為は、自然(花)に対して何もいいことをしていないし、人間の一方的な思惑であるに過ぎない』というフレーズだ。続けて『ただ人間は植物を切って、移し、飾るということで、自然を深くイメージ出来る。しなやかでありながら、到底制御しきれない屈強な自然に触れることで、「生」や「死」、「地球規模の自然サイクル」に至るまでを見い出そうとしているのではないか』と。まさに3.11以降の今日においては、琴線に触れる言葉である。伝統的な「華道」の枠をぶち破りながら、「華道」の本来の精神や考えを皆に継承して伝える上野の姿がとても印象深かった。
斜に構えた涼しげな美術表現とは、明らかに一線を画する上野ならではの表現活動は、これからも創造と破壊を繰り返しながら、人の道、すなわち「生」や「死」の生々しさを表現し、自然界との交差を体現しながら、さらに走り続けるのであろう。
会期最終日の夕暮れ、これまで共にした集落の人々やスタッフが集まりバーベキューが行われた。当初は、シンボリックに走り回った「暴走花いけ限界号」の枝木をここで燃やす目論見だったらしいが、まだ引き合いがあるという限界号の枝木の代わりに、オープニングで農舞台ギャラリーの屋上に立てた杉の木などを燃やすこととなった。里山に発光する炎を囲み、最後の挨拶をする上野が感極まって言葉を詰まらせたシーンは今でも忘れられない。つねに「気」を込めて人にも表現にも前向きに接する上野雄次の姿勢を象徴するエピソードだ。ひとつの「祭」が終わり、見渡せば遠く山々の輪郭を映す夕刻の空が、紺色に輝いている。それは、彼のパフォーマンス同様にとても神秘的で神聖な時間であった。
[文・鎌江謙太]
※1 暴走花いけ限界号
自家用車に枝木をいけた自走する「花いけ」作品だ。そのルーツは昔の貴族階級が御所車に花をいけた「花車」を現代に見立てているという。奇抜なシルエットだが、積載・車高制限をクリアし都内などでも普通に走行している。
※2 脱皮する家
この建物自体、日本大学芸術学部絵画学科彫刻コース有志の学生により作品化された築150年の農家民宿なのだが、床、柱から天井の梁にいたるまで、気が遠くなるほどに建物の全てが彫刻刀で細かく刻まれている。その作業は、3,000人工を要するほどの作業だったいう。夏の青青とした里山の限界集落に、すっかり溶け込む佇まいだが、無数に刻まれた「記憶」ともいえるタッチとともに新しい手触りを加えられ、まさに脱皮(再生)した古民家だ。