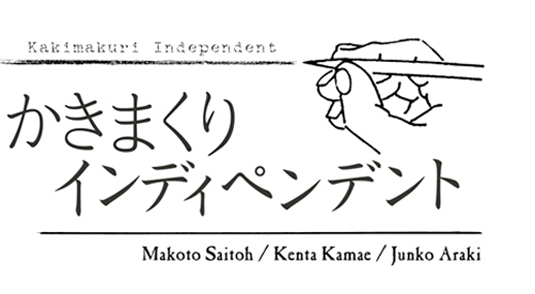03
美術批評「物々交換所の創造性」
文:斉藤 誠
今から5年前、当時まだ大学生であった美術家の酒井貴史は、《物々交換所》という活動を始めた。きっかけは学内に捨てられていた資材を見て「もったいない」と思ったことだ。そこで試しに大学構内に物々交換所を設置してみると、思いの外どんどん貰い手がついた。そこに楽しさを見出した酒井は卒業後に活動を本格化させていく。《物々交換所》とは、読んで字の如く、物と物を交換するための場所である。誰でも不要になった物を《物々交換所》に置くか、または、欲しいものがあれば持って帰ることができる。これを芸術作品と見るかどうかは意見の分かれるところだが、第三者同士が物と物を交換する行為自体を酒井自身の表現として解釈することはできる。しかし、こうした解釈では何か物足りない感じが残る。もっと大きな可能性があるように思えるのだ。
そこで、まず実際の《物々交換所》を訪ねてみる。横浜の黄金スタジオ内にある《物々交換所》には、青色のアイコンと不要品を置くためのラックしかない。ラックには、雑誌、ぬいぐるみ、ランプシェードをはじめ結構な物量。専任のスタッフはおらず、必要最低限のルールが記載されているだけだ。一見するとやや無味乾燥な印象を受けるが、この無色透明性こそが《物々交換所》の特徴だ。1週間後に再び訪ねると、すべての品が入れ替わっていた。黄金スタジオのスタッフによると「毎日のように訪れるファンがいる」そうだ。
そして、ネット空間にはもうひとつの「物々交換所」がある。と言っても、ネット上で物を交換させるわけではない。リアルな《物々交換所》からは人と人との交流が生まれにくいため、補完的なコミュニケーションツールとしてソーシャルメディアを用いているのだ。物の流通を促すための潤滑油としての側面もあるが、面白いのはそこで交わされる会話。「鍋が欲しかったが蓋だけだった」といったネタ的なものから「世の中お金がなくても生きていけると思った」という物々交換そのものをめぐる意見まで、さまざまな書き込みがあふれている。
このように、《物々交換所》はリアル空間とネット空間により構成されるひとつの体系なのだ。人々は双方の空間を行き来しながら交換を楽しむ。そこに見受けられるのは一種のゲーム感覚だ。設置運営者の酒井でさえ「1プレイヤー」にすぎない。彼自身、着るものすべてを《物々交換所》で調達しているほどだ。共通の目標を持たずとも、ゲームに参加することで、結果として物々交換という運動が進んでいく。したがって、ゲームへの参加のしやすさが問題となるが、前述した《物々交換所》の無色透明性がそのキーポイントとなっている。
《物々交換所》はその性格上、反消費主義やエコロジーな観点から捉えられがちである。しかし、酒井は「あえてそうした主義主張を込めないようにしている」と言う。もし仮に「循環社会の構築に寄与するため」などと活動目標を謳っていたなら、賛同する人もいる反面、興味のない人たちを疎外してしまうだろう。そうではなく、誰もが気軽にコミットすることができるよう配慮することで、《物々交換所》に関わる人自身が意味を見出す余地が残されているのだ。そして、その空き地からは無数の小さな物語が芽生えてくる。たとえば、次のような話がネット上に綴られている――。彼女はいつも《物々交換所》でシャツを探している。見つけると持ち帰って刺繍をした上で《物々交換所》に置いてくる。そしてまた違うシャツを探して刺繍を…、ということを繰り返す。自分が刺繍をしたシャツを着て歩く人を見たい。その日を彼女は心待ちにしているのだ。
※本稿は、「HAMArt! vol.6」(2012年10月発行)に掲載された記事です。